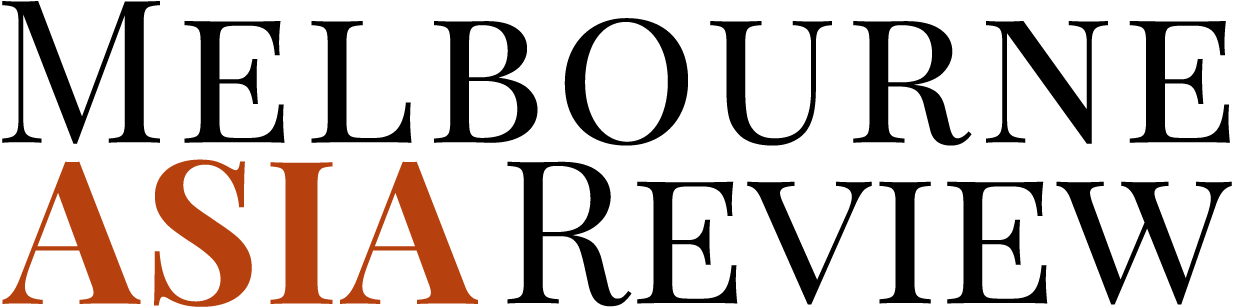翻訳:Zihan Chen, Tien Kim, Julia Licup, Kaori Weightman
監訳:飯塚 俊太郎(Shuntaro Iizuka)
日本の刑事裁判は、過去20年間に及ぶ大規模な法改正の結果として当事者主義へ移行した。弁護士は、市民の陪審員としての役割だけではなく、専門の裁判官と同席する市民裁判員という新たな形式からなる職場コミュニケーションに適応しなければならなくなった。弁護側と検察側にとって、説得力のある法廷パフォーマンスとコミュニケーション戦略で「戦いに勝つ」必要性が課題となってきた一方で、裁判官は真実を追求する捜査上の権力を保持している。本稿では、当事者主義への移行が裁判所でどのように現れているか、法廷で要請される重要な口頭コミュニケーションおよび、伝統的に刑事司法のプロセスで中心とされてきた書面でのコミュニケーションへの信頼に関するジレンマについて論じる。
「ハイブリッド」な日本の刑事司法
日本は、19世紀末の封建時代から明治維新への移行期に、フランスとドイツを基として刑事司法を打ち立てた。日本は糾問的、すなわち大陸法体系という法的制度を採用し、裁判所には国の調査官とともに「真実」を追求する役割が与えられた。第二次世界大戦の敗戦後は、アメリカのコモン・ローに従い、日本の刑事司法に当事者主義の要素が導入された。この制度では、被告人は通例、弁護人に代理され、裁判所に証拠を提出し、合理的な疑いを超える有罪が証明されるまでに無罪と推定される。
日本語の「当事者主義」は、文字通り「当事者の原則」か「主導権を当事者におく原則」という意味を示し、英語では主にadversarial systemと翻訳される。当事者主義の裁判では、検察側が立証責任を持ち、両側が証拠と証人を提出し、裁判官は「中立的な」審判官として法廷手続きを司る。証人は通常、両側から尋問されるが、争いのある事件では、証人は弁護士からの執拗な尋問の強いプレッシャーにさらされることもある。
弁護士が利用するこのような戦略的な修辞法や尋問の仕方は、日本の刑事裁判の「敵対的」側面を特徴づけている。コモン・ローの当事者主義における裁判所・法廷の言葉を研究してきた学者たちは、裁判所を、物語を競い合う戦いの場として特徴づけている。重要なのは、どちら側が陪審により説得力のある物語に証拠を織り込んで、提示できるかということである。
日本で保たれてきた審問型の裁判の特徴は、弁護士の尋問の後、裁判官が証人に「補足質問」をすることである。これは、弁護士が取り上げなかった犯罪や事情に関連する詳細を発見することを目的とする。このことは、裁判官が尋問を通じての「真実発見」の道を追求しないオーストラリアのようなコモン・ローの敵対的裁判制度に慣れ親しんだ人々にとっては驚きかもしれない。このような追求しようとする姿勢は、(訳注:コモンローの)弁護士にとっては、裁判所での法的プロセスに対する当事者主義のアプローチを「台無し」にするかもしれない。
伝統的に、裁判において口頭でのコミュニケーションがより重要とされるアメリカやオーストラリアのようなコモン・ローの司法に比べ、大陸法の司法は、書面により依存している。証人は直接尋問され、弁護人は各裁判の最後に弁論を読み上げるものの、日本の刑事司法プロセスは、警察や検察が採取した自白に基づく被疑者および目撃者の供述調書に過度に依存しているという批判がある。実際に、17年以上の服役の末に無罪となった菅家利和の事件のように、近年、調書の形で提出された虚偽の自白が原因で無罪となった例もある。菅家は1990年に起きた少女殺害事件の被告となり、裁判前に自白を提出したが、裁判では否認した。新たなDNA証拠と取調べの録音テープによる再審の結果、彼は無罪と証明された。しかし、警察の調書への過度の依存は、主に1999年に始まった司法改革によって、近年変わってきている。
激しいやりとりの場という法廷への移行
司法制度改革審議会 (1999–2001年) における大規模な司法改革の一環として、日本の司法プロセスへの市民参加は、2009年の裁判員制度の導入で実施された。それにより、裁判への市民参加が再開された(日本における陪審制度は短時間だけ (1929ー1943年) 行われたことがある)。このような改革の背景には、日本の刑事司法制度における人権問題の改善を求める国際社会からの圧力のほか、法定制度を改革する必要性の認識もあった。そのため、裁判員制度と共に、法科大学院や日本司法支援センターの設立がなされた。
裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、身代金目的誘拐罪等の重大な刑事事件である。裁判員候補者名簿の中から選ばれた裁判員6人が、裁判官3人と一緒に裁判を行う。裁判員は、被告人が有罪か無罪かを決定し、有罪の場合は量刑の判断をする。裁判員裁判が頻繁に実施されていないのは事実であるにも関わらず(地方裁判所の裁判員裁判対象事件の全新受人員における新受人員に占める割合は2018年に1.6%であった)、市民の司法参加制度の導入そのものは、多くのメディアで大きく取り上げられた。それに加え、裁判員裁判に関する情報を市民に広げるために行われた強力なキャンペーンの影響で、日本の司法制度とその諸問題も、日本中の注目を集めた。
2009年(平成21年)裁判員制度が導入された後、日本の法廷におけるコミュニティースタイルには変化が生じた。当事者主義の裁判は、やりとりの激しさが特徴的で、コミュニケーション戦略が強力な武器となる。より説得力のある陳述には、効果的な尋問戦略を証人尋問の際に行うことが必要である。証人や被告人の供述と矛盾する点があれば、それを明らかにするように、質問の順序について慎重に検討しなければならなくなる。弁護人としては、主尋問における誘導や、真実と異なる表現に異議を唱え、相手方弁護人が早い段階で述べた証言の誤りを撤回して訂正することを求める。しかし、自分の味方である証人が質問される際には、話が本題から逸れたり、相手方弁護人にとって有利な供述が出たりすると、弁護士はその場で証人の話を切って発言を控えるのである。
筆者がフィールドワークで傍聴したとある裁判員裁判で気付いたのは、重要な情報を引き出すための誘導尋問のやり方である。強盗致傷罪として起訴された被告人は、自分の腕と被害者の首との位置関係を尋ねられた際に、彼の陳述と供述証拠との矛盾が発見され、相手方の検察官に「被告人の首を強力に絞めたのではありませんか」と質問された(以下の引用は筆者による英訳である(訳注:本稿の原文は英語))。それを認めた後、被告人は「首を絞めるような行為を行なったということですか」と再び質問され、「はい」と答えた。その後、一緒に転倒した時に被害者の身体の下にあった腕の位置について、被告人に「被害者の首を絞めていた際にバイクを見て腕を抜こうとしたことはありませんか」と相手方の検察官は更に問い詰めた。このような否定的質問は、強制力があり、被告人の主張の信用性を低下させるように働くのである。被告人は、その質問を否定し、相手方の検察官の訴状の受け取りを拒否した。
それに次ぎ、被告人の注意を引くために何度も財布を掲げても取ろうとするつもりがなさそうというのは被害者の証言だったのではないだろうかと、相当詳細な質問を被告人方は言った。また、「被告人は財布に気づきましたか」と問い詰めされると、「[…]何度見せても取られなかったです」と女性の被害者は答えた。その後、被害者が財布を持って被告人に「強くアピールしました」と被告人方は陳述した時、検察官は、「彼女は『強く』と言ってなかったです」と被告人方の話を切った。このような法廷独特の言い回しは、その重要性が当事者双方の争論から明らかになるのである。以上は、法廷での激しいやりとりの一つの例であり、当事者主義に比べて審問主義の裁判員裁判の方でよく見られるのである。この種の口頭弁論は、裁判員制度の導入前にも、特に争われた裁判の場合に発生したのは勿論のことだが、近年になってより一般的になってきた。それで、法廷における権利擁護のスキルの研修の量と裁判員制度による変化に対する弁護士の認識は、当事者主義の法廷のコミュニケーション能力に対する意識と実践力の向上を映し出す。裁判員制度以前は、法廷外で、職業裁判官が証拠型の書類(警察の供述を含む)に頼ることの方が多かったが、裁判員裁判ではそうとは限らない。
当事者主義におけるもう一つの特徴は、含蓄のある言葉を使う戦略を用い、被告人、証人、被害者に関して望ましいイメージを作り出すということである。裁判員裁判を傍聴した時に気づいた一例をあげるならば、検察官は傷害致死罪で告訴された被告人を「王様」、被害者を「下僕」や「家来」や「召使い」と描いたが、弁護側は「友達」かのような関係を表現した。検察側は被告に証人と亡くなってしまった犠牲者を脅すというイメージを描いたつもりなのに対し、弁護側は社会的で道徳的な性格を持つように描いた。検察側の証人の一人は、検察の質問に被害者と被告の関係について「まあ、親分と子分か召し使いの関係のようだった」と答えた。また別の証人は、「召使い」のように扱われたと主張し、最終弁論でこの被告も「召使いのような扱い」をされていたことも言及された。
こうした裁判員制度に対する法廷での談話のこうした特徴は、日本の裁判で口述が重視されるようになっていることを示す。必要なパフォーマンススキルは質問スキルや力強い叙述を作ることばかりでなく、他の記号論的なリソースを有効に活用し、例えば非言語コミュニケーションや視覚補助などの使用を含んでいる。弁護士会の研修では、姿勢の指導、アイコンタクトの仕方、立ち位置、「ペーパーレス化」などが学ばれており、アメリカの国立法廷弁護研究所(NITA)による権利擁護へのアプローチがしばしば参考されていた。
私の傍聴した多数の裁判員裁判では、弁護人が自分の席の遠くに行き、裁判官のベンチの前で最終弁論を演説していた。その方法は裁判員制度以前には滅多に見られなかった方法であり、実に演技的なアメリカ式の実務の影響で、日本弁護士連合会のいくつかの支部で推奨されたものである。しかし、興味深いことに、検察官は、常に机の後ろで冒頭陳述と論告を演説していた。立証責任が検察側にあることを考えると幾分逆説的だが、日本では、おそらく、検察官は、裁判官にアピールするためのさらなる別のコミュニケーション戦略を用いる必要がないのかもしれない。
口頭と書面のコミュニケーション・モードの緊張関係
日本の刑事司法制度において、法廷でのパフォーマンスとコミュニケーションスキルへの重視が増加していることは明らかだが、同時に、裁判員の役割が刑事裁判全体に占める割合は少ないことを認識することが重要である。職業裁判官によって審理されたケースが大部分を占め、これらの裁判官は主に警察と検察の記録に頼っている。
それにもかかわらず、裁判員裁判は裁判官のみによる裁判に波及効果をもたらし、証人の直接尋問が一般的になる方向への移行が進行しているようだ。これは、警察や検察の記録(調書)に依存する方法から脱却しようとする動きでもある。裁判官は従来からこれを利用しており、いまでも、法廷外で読むことがある程に行われている。しかし、2016年以降、裁判員によって審理される事件には警察と検察のインタビューの視覚・音声記録が義務化され、口頭審理への移行は刑事事件の捜査段階でも徐々に顕著になっている。
ただし、法廷内での口頭コミュニケーションと非言語コミュニケーションが重視されるようになったことが、すべて良いことだとも言えない。一部の弁護士は、証拠の完全かつ正確な提出の代償として、法廷におけるパフォーマンスに過度に依存することへの懸念を表明している。そのようなアプローチは「演技的」と見なされることがある。特に経験の浅い弁護士の場合、裁判官とのアイコンタクトが「無理に感じられる」とか「あまりにも目立ちすぎる」と見なされ、不自然に思われることがある。このジレンマを解決する一つの方策として、裁判員裁判では、冒頭陳述と最終弁論において、裁判員に証拠と係争事項を示すために、パワーポイントや配布資料などの視覚的資料を使用することが一般的に採用されている。
例えば、ある裁判員裁判の最終弁論では、双方の弁護人が「メモ」という配布資料を配布し、重要な「ポイント」を示し、ときに数値を示していた。例えば、「メモ1をご覧ください、争点が記載されています。・・・ 今から説明します。ポイント1をご覧ください・・・」といった具体的な方法で進行した。こうしたハイブリッドなアプローチの問題は、当事者主義の「演劇的な」または「パフォーマンスな」要素と必ずしも相容れないことだ。配布資料内の特定の句に裁判官の注意を引くような明確な要求は、裁判官が弁護士と目を合わせることを防ぐ一方、説得力ある非言語コミュニケーションの役割を低下させる可能性がある。もちろん、日本の刑事司法制度において、経験豊かで効果的な法廷コミュニケーションスキルを持つ上級の弁護人が存在し、特に、検察官の権力に対抗できる弁護人もいる。だが、実際、裁判官の役割はほとんど判決に制限されており、無罪判決の割合は1%未満である。
しかし、特に裁判員の法廷手順の理解に関しては、書面でのコミュニケーションを用いつつ、口頭コミュニケーションを改善することで、法的手続きは改善し得る。裁判員裁判は通常連日行われ、疲労と理解の問題を引き起こしかねない。裁判員としての日々の終了後に長い最終弁論を聞くことは、裁判員が最終結論に向けたすべての必要な要点を理解し判断する能力に影響しているかもしれない。実際、法律と法律の言語の専門家は、長らく非法曹の法的言語に関する理解の問題を議論しており、裁判員への指示の書面バージョンや法廷コミュニケーションの理解を支援するためのさらなるリソースの提供を勧める提案がなされている。日本の裁判員法(第51条)は、裁判員に対して「審理を迅速で分かりやすいものとする」ことを裁判官や弁護士に義務付けている。
日本におけるハイブリッド型の裁判員制度は、口頭コミュニケーションがより強調される他の国々や地域における非法曹裁判員制度に示唆的かもしれない。ただし、現行の法的手続きの制約からは、概要の配布資料などの補助ツールが含まれない可能性があるようである。
法的プロセスにおいて変化する力関係の影響
変化するコミュニケーションスタイルが裁きを与えることにどのような影響を与えるのか、そして日本の法制度が大規模な変革に伴うコミュニケーションの課題と可能性をどのように受け止めるのかは大きな問題である。
上述のように、日本は一貫して高い有罪判決率で知られているが、米国や他のコモン・ローの国や地域と違い、罪を認めている被告が裁判にかけられることになる。弁護側は犯罪の悪質さを争い、総じて情状酌量を求めることがあり、コモン・ローによる裁判に比べ、法廷で起こる「バトル」の性質は少々異なる。裁判員制度は有罪判決率に大きな影響を与えておらず、時として、裁判員制度の時代以前よりも刑罰が重いこともある。その上、公判前整理手続きが検察側に有利であり、裁判官が未だに検察官と協力的な関係でありがちであることは、法学者がよく論じてきた。
とはいえ、弁護士には検察官が持つような制度的な支援はないものの、より多くの弁護士が法廷でのコミュニケーション戦略の訓練を積めば、おそらく裁判員制度によるメリットを受けることになる。
この変化が日本社会に与えた影響は見過ごすべきではない。裁判員裁判はメディアで広く報道されており、また、自分が裁判員として裁判に参加する可能性があることから、刑事司法プロセスに関する啓発をする人が増えた。法的プロセスや司法システムにおけるコミュニケーションに目を向ける人も多くなっている。
Image: Supreme Court of Japan: Image credit: 江戸村のとくぞう/WikiCommons